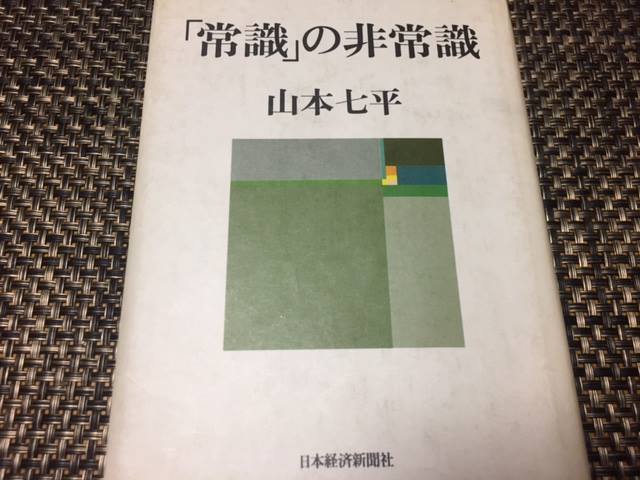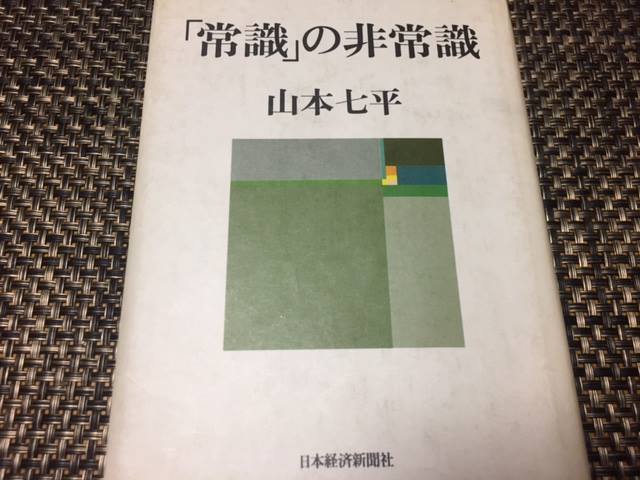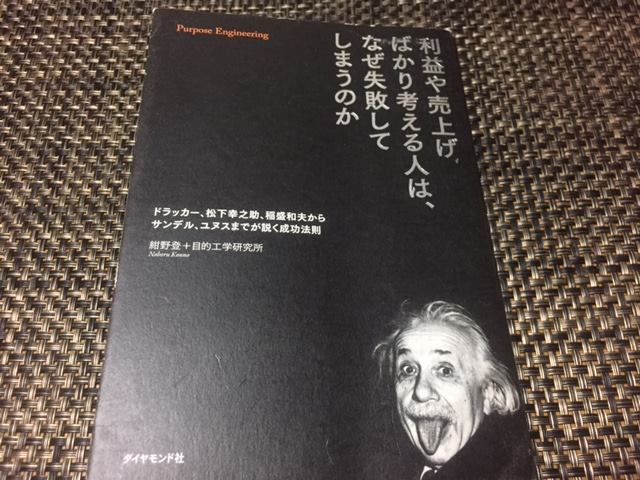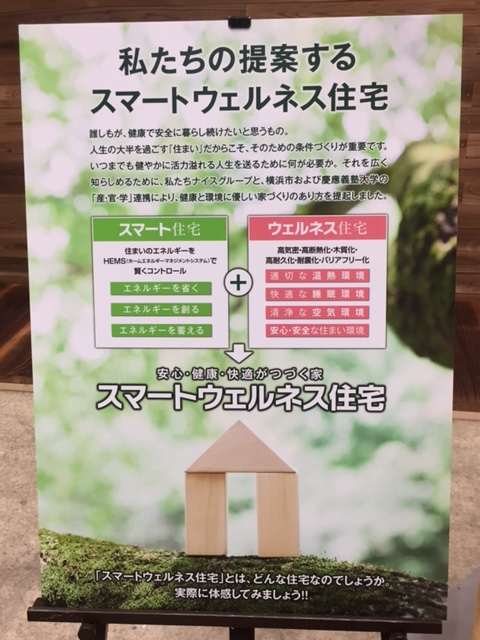2017年2月19日 『第3の道』
前々回、前回の夜話は「志」「新しい目的」でしたので、その実現に深く関係する「未常識と非常識」をテーマにしました。
「価値創造」にとって、「常識」を離脱・逸脱することは必須なのですが、それにまつわる痛い体験を二つ綴ります。
1.第10夜詳細:「オーディオのイノベーション」
1992年の経営会議で、
「2005年前後を境にして、オーディオはCDの時代から、超高密度メディア(USBメモリ)や通信の時代に移行する可能性が大きい。
その為の準備を2000年までに行いたい」
という旨のプレゼンテーションを委員会メンバーを代表して行いました。
当時はCD全盛の時代ですから、すぐに担当部長に呼ばれて、
「橋本よ、そんなことは起きるはずがない」と。
その報告は非常識に思えたのでしょう。
その担当部長が退職されるときに、私のところにきました。
「お前が云うとおりになったな」
その時に、返答したのが、
「それは未常識だっただけです。超高密度メディア委員会メンバーのシミュレーションをただ図解してお伝えしただけです」と。
2.第14夜詳細:「社長直訴そしてヒット商品緊急プロジェクトへ」
1990年移行、ホームオーディオは衰退期に入っていました。
そこで、「『性能・機能』ではなく、『効能としてのライフスタイル』をベースにして、異業種コラボレーションでヒット商品を生み出す」
という提案を1995年の経営会議で行いました。
その後に、ある役員からお呼びがかかり、
「新社長がOKしても、こんな提案が上手く行くわけがないだろう。
一体、何を考えているんだ・・・・」
次々に厳しい言葉が続いて浴びせられました。
今、「目前にある課題・問題」に集中して、それを解決することを責務として事業を任せられている人からみたら、そのように映ったのもわかります。
ただ、第13夜「倒産、そして新価値創造」を体験してきた自分からは、
「役員の人達が退職するまではそれでいいかもしれないけれど、その後に残った多くの若い社員や家族のためには、今ここで新しい目的のために行動に移さなければならない」
という熱い思い(志)がありました。
役員からみたら、良からぬ非業、非常識に見えたでしょう。
どちらも自分からの常識から見ていたのです。そして、私の方は「後になれば判る未常識」だったのです。
①は時間軸で、②は対立軸で「常識とは何か」を教えてくれます。
そんな『常識』『未常識』『非常識』を教えてくれたのが、写真の本です。
それは31年前、つまり自分が30歳の時に出会った山本七平さんの著書です。有楽町にある本屋さんで、何故かこのタイトルが気になり、「常識の研究」「常識の落とし穴」と後に続く常識シリーズに夢中になりました。その後の自分の「常識を超える未常識」の基盤になりました。
丁度、「倒産、そして価値創造」(第13夜)に記した前職・パイオニア社の当時2000人規模のセンター工場で労働組合の支部書記長をしていた頃です。
30~35歳の時は、家に帰ってもなかなか眠れずに、夜中の2時くらいまで起きていて、自分の磨き方、生き方や将来の道筋を考えて悶々としていました。
組合執行部の会議の合間にその話しをしたら、「オレも、オレも」と相槌があり、自分だけではないのだと嬉しくなったことを思い出します。会社人生のその時期は、「次のステップへの大事な時」なのですね。きっと。
さて、山本七平さんは「常識」について次のように記しています。
------------------
「常識」とは分析不可能なものであり、また明治になってできた言葉です。小林秀雄によれば、徳川時代には「常見」といったそうです。[反対語は断見(だんけん)]
常見(コモン・センス)の「センス」は「識」よりも「見」に近い。私達は確かに「常見」の世界に生きていて、「常見」で世の中、世界を見ている。
ただ、「見」は必ずしも「識」ではない。視点を違えて別の見方をすれば、「常見」とは違う面が見える。このさまざまな「見」を総合して判断を下せば、そこにははじめて「真の常識」が成り立つであろう。
------------------
事例を二つほど記します。
1. 量の変化が質を変える
日本の高校進学率は、経済成長とほぼ同一カーブで上昇し、昭和30年50%、40年70%、50年90%となっている。これを量の問題として捉えると、これに対する教育施設の拡充、教員の補充といった問題になり、それに対応するのに大わらわになる。
その時、量に対応すれば問題が解決するのではなく、ここで問題の質が変化するのだとは、殆ど誰も考えない。
いわば、それ以前はもちろん、クラスの50%が高校に進学する時でも、残りの50%は、自分たちは「落ちこぼれだ」という意識は持たないし、社会もそういう目では見ない。
ところが90%前後高校進学となると、そうはいかない。ここで問題の質は変わり、これは教育施設の量の拡大では対応できない教育問題となってくる。
2.「二者択一以外」の道
日本に、カモシカ問題がある。同じようにどの国でも、絶滅に瀕した動物を保護すると、急速に増加するが、今度はその動物による食害問題が起こる。
すると、保護をやめて一定数以上は射殺・捕獲すべきか、あくまで保護すべきかが当然問題になる。日本でも檜の苗木をばりばり食べられてしまえば、山林業者にとってはカモシカは害獣ということになるであろう。保護を続けるなら、山林の保護をどうするか、業者への損害保障はどうすべきかが当然問題になる。
そして、こういう場合、議論はしばしば保護か、捕獲・射殺かの二者択一になりやすく、多くの場合、両者とも自説を固持して譲らないという対立になりやすい。
これはすべての問題についていえる。環境問題、貿易問題、また企業内の問題、各人の抱える問題、そのすべてについて、問題が二者択一のように見えてきたら、そのいずれでもない「第3の道」があるのではないか、ともう一度、探索してみる必要があるのであろう。
上記二つには、ビジネスのイノベーション・価値創造の本質が記されていました。
・「量」が、一定の水準を超えると、「質」が、劇的に変化する(第10夜、第11夜、複雑系)
・「矛盾」とは、発展の原動力“矛盾の止揚”である(第15夜、第17夜、第18夜)
この「質への変化」「矛盾の止揚」の視点・視座を柔軟に活用できることが、創造性「クリエイティブ&イノベイティブ」(第1夜)への本筋です。
ただ、実際の現場では、それまでの「常識」で成功した人達や組織が存在して権力(既得権)を持っているので、新しい「常識」に移行するのが遅くなったり、困難になることがあります。
さて、そこで重要になるのが、「何が変わって、何が変わらないのか」という認識です。特に、「何が変わらないのか」ということを共通認識することが移行をスムースにさせることが多いことを経験しています。
その双方をトップが認識されて、リーダーシップを発揮している会社は、卓越した機動力があります。
さて、本研究所の研修・セミナーでは、それまでの「常識」という分厚い黒い殻を破る心得と方法を先ず最初にお伝えしています。(コメントに追加しています)
そこでのポイントは、「これまではこうやって上手くやってきた」という従来のやり方や考え方を捨て去り、常識の壁を破り、その奥にある「3つの本質」を掴み取ることです。(第11夜)
それが価値創造の「トリニティ・イノベーション」(第21夜)です。
さて、山本七平さんは、あの有名な「日本人とユダヤ人」の作者とも言われています。
特に、明治維新という大変化の前後で起きた価値観の変化や、武士以外の庶民がどうして上手に対応できたのか、ということも分かり易く説明されています。
その示唆は、現在生じている日本や企業の課題や、これから起きるであろう諸問題への対応にはたいへん有効です。
30歳の時に、山本七平さんの書物から、ものの見方や考え方、特に「第3の道」に触れられることができたことを幸せに思います。そして、是非、若い方達にもそれらを経験して欲しいと思っています。
第29夜・価値創造による経営革新