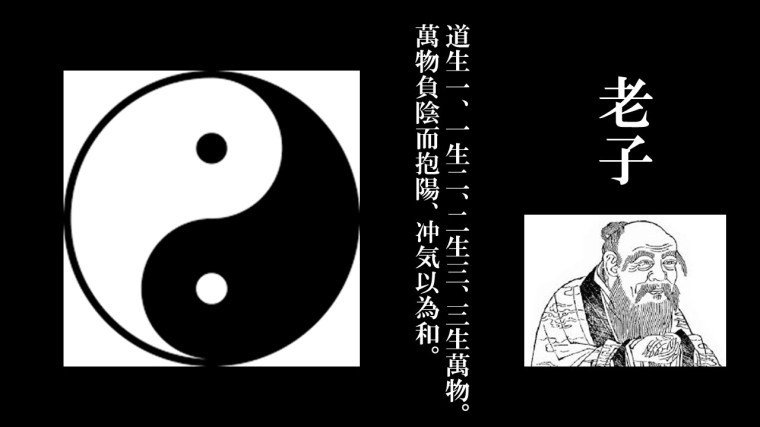2018年11月14日 能と価値創造
世阿弥は、室町時代に『能』を大成した人物として知られています。
『風姿花伝』は有名ですが、その「花」とは「価値創造」のことを云っています。
本夜から、世阿弥の知を「能と価値創造」の関係で綴っていきます。
『能』と自分との本格的出逢いは、松岡正剛師匠主宰の「未詳倶楽部」にありました。
・1回目は、大倉 正之助(おおくら しょうのすけ)さん
・2回目は、安田登(やすだ のぼる)さん(下掛宝生流ワキ方能楽師)
2000年、未詳倶楽部の特別ゲストが、囃子大倉流大鼓方能楽師の人間国宝・大倉 正之助(おおくら しょうのすけ)さんという大鼓(おおつづみ)打ち手の達人でした。
初日の深夜の空間では、自分から2メートルの至近距離から、大倉さんのソロの大鼓(おおつづみ)が響きました。その「幽玄」を身をもって堪能しました。
2日目は、大鼓(おおつづみ)を素手で打たせてもらうという体験もしました。「響打」の奥義がほんの少し体感できたように想いました。
その興奮を持って、2000年8月8日、大倉さんと松岡正剛師匠がプロデュースする「五番能」(五番立)と呼ばれる本格的な形式での能公演(宝生能楽堂)に行きました。
「翁附五流五番能」に寄せた松岡正剛師匠のテキストを引用します。
……………………………………………………………………………………………
「観能から官能へ~こんな一部始終を見てみたかった」松岡正剛(編集工学研究所所長)
いまどき五番能が見られるだけでも珍しい。
それが五流が揃い、さらに「翁」が付いている。
神事から始まって、しだいに修羅へ、切に突き進む。
異例中の異例な出来事だといってよい。
その翁附五流五番能を、一度も演能祭事のどこにもかかわったこともない私が、なんとも提供する側になるとはおもわなかった。
すべては大倉正之助の六輪一露なのである。
いやいや二輪双輪のエネルギーが飛び散ったせいである。
細部に関してはまことに面食らうばかりであるが、ただただ大倉正之助の邁進の企画に呼応して、拍子を合わせた。
はからずも打ち合わせたというしかない。
なにしろたった一人で大鼓を打ち続けようというのだから、これは放っておけぬのである。
しかし、一介の囃子方にすぎない大倉正之助の魂が実現させたこの五流五番能は、前代未聞の試みでありながらも、実は能を初めて見るような人々にこそ開かれている。
私としては、これを機会に能狂言の持つ意味が一途に見所にいる人々の心を奪っていくことを願ってやまない。
そこには「日本」というもののいっさいの不思議が現前に漂泊しているからだ。
実は能というもの、まことに不合理にできている。
ありていにいえば不便にできている。
たとえば面は、わずかに前方は見えるものの、他の視界を許さない。
その面の動作もテル・クモル・キルなど、ごくわずかな動きに限定されている。
音楽としてとらえてみても、小鼓は湿らせなければいい音が出ないし、大鼓は焙じて乾かす必要がある。
だいいち、アンサンブルとしての基準音は最初の能管の一吹きがあるまでは、決まらない。
こんな音楽は西洋の合理では考えられないことである。
リズムとしての拍子だって、大きなフレーズごとにインとアウトが決まっているものの、あいだはまちまちである。
だからこそ、そこに間というものが躍り出す。
一調二機三声が動き出す。
登場人物も、多くが現在にはいないことによって現在を示すというような、そんな奇妙な設定の中にいる。
そこで、そこには現代哲学こそが主題にしそうな「不在の時間」というものが出現するのだが、ではその時間が舞台をそのまま支配するのかというと、その不在すらもあとかたもなく消えていく。
舞の基本もカマエとハコビだけである。
そんなことでよくも感情が表現できると思うだろうが、けれども、そこにヒラキが加わるだけでも、引きつめた緊張は横超し、悲嘆は爆風をおこすかのようなのだ。
装束もまた、そのようなあまりにも省かれた劇空間と劇時間を暗示するかのように、長絹・舞衣・狩衣・直衣のいずれもが、行方定めぬ風をはらむばかりとなっている。
こうした不合理や不便を象徴しているのが能舞台そのものであり、能なのである。
その不便をわずかなキマリが支えている。
たとえば、橋からやってきた者は橋から去っていく。
これは、かれらが彼方からの去来者であることを訴える。
たとえば五番能の二番目は修羅能というものであるが、これは世阿弥が二曲三体と言った、その老体・女体・軍体のうちの軍体を見せている。
修羅の能は平家物語を背景とした「いくさがたり」がルーツなのである。
もっと単純なことをいえば、だいたい舞台は誰も隠れるところがない。
すべては見所から見通しであって、そこには真の意味での「一部始終」というものがあるばかりなのだ。
しかしそれゆえにこそ、キマリは奥深くなっていく。
いっさいのキマリが見えているようで見えていず、見えないようであらわれてくる。
その僅かな出処進退が、能舞台をおそろしく絢爛とも、幽玄とも、またヴァーチャル・リアルともさせるのである。
そのダイナミックな有為転変は、不合理や不便によって生まれたのであった。
私は、その奇妙な矛盾の解放をこそ見てほしいとおもう。
そこに能狂言が培ってきた乾坤一擲の「存在の告示」があることを見てほしい。
それこそがいま「日本」に欠けているものなのである。
ところで今日の演目には、いずれの物語にも「水」がからんでいる。
この「水」は流れであって、生命の若水であり、そして自然と人知を循環する媒体である。
大倉正之助が八年前に、これらの水を湛えた演目をしたかったという意志をもったことにちなみ、今日の一日を「如水の昼夜」とよぶことにした。
また、今日一日の出来事には、人機が一体となって感応するオートバイの魂のようなものが、そこかしこに象徴化されている。
なぜ能とオートバイが重なったのかということをここで述べている紙数はないが、きっと今日の日が終わるまでには、その人機一体の官能が実は観能でもありうることを、ひたひたと感じられるのではないかとおもう。
私が、早朝の「翁」が始まる前に言えることはねいま、これだけである。
いろいろな「一部始終」を観能し、官能し、堪能していただきたい。
……………………………………………………………………………………………
上記のテキストを見ることだけでも、深み・高み・広みが伝わってきますね。
プロデュースされた『別格の一流』を観能し、官能し、堪能してきました。
そのような直截的・直観的な体験と知が、「価値創造」には肝要です。
さて、「能」舞台の橋の向こう側は、there・彼岸です。
複式夢幻能において、能舞台は、死者と生者が交じり合っている「場」なのです。
舞台の正面には、「松」の絵が描かれていますが、ということは観客席は「海」にいることになります。つまり、私たち観客は、there・彼岸から観ているのです。
そのような「しつらい」を認識して身を置いて「能」に対した時に、目の前の風景・情景が変わってきます。
そこには、「生と死」の狭間の情念と夢と想像が行き交います。
本夜は、世阿弥のことは、まだ記していません。
自分にとっての「能」との切っ掛けから綴りました。
価値創造から、「事業創生・地域創生・人財創生」へ